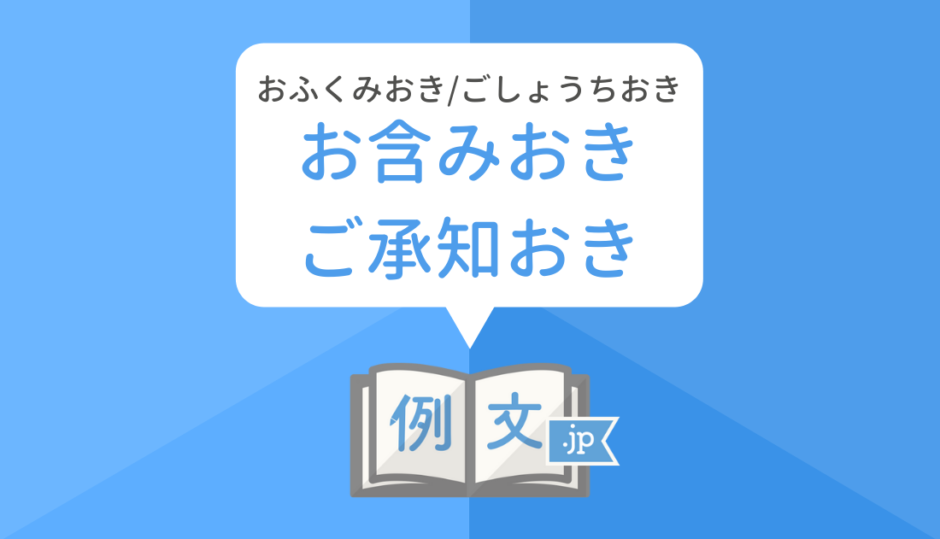目次
お含みおき の意味とは
ビジネスシーンなどでよく聞く言葉に「お含みおき」があります。お含みおきください、などのフレーズで聞いたことがある、という人は多いでしょう。
まずは、この「お含みおき」の意味について解説します。
お含みおきとは「心の中に留めておいてください」
「お含みおき」とは、心の中や頭の片隅に留めておく様子を意味します。
この「お含みおき」の原型である「含みおく」には、自分の気持ちや思いを心に秘めておくという意味があります。この「含みおく」を敬語にしたものが、「お含みおきください」です。
「お含みおきください」には、「心に留めておいてください」「理解しておいてください」「納得しておいてください」という意味があります。
「お含みおき」は目上に失礼になる?
「お含みおきください」を目上に使ったとしても、即失礼な言葉として受け取られることはありません。
「このことを心の中に留めておいてください、頭の中に置いていただけるとありがたいです」というニュアンスなので、目上の人に必要なことを知っておいてほしい場面で使えます。
しかし、相手に含みおいてもらいたい内容に相手が納得をしていない場合や、理解ができてない様子であるにも関わらず「お含みおきください」と言われると、やや押し付けられた印象を受ける人もいます。
![]()
お含みおきの例文
ご承知おきの意味とは
先に解説した「お含みおき」と似た言葉に「ご承知おき」があります。この「ご承知おき」はお含みおきととても似た言葉ですが、意味が微妙に異なります。
以下では「ご承知おき」の意味について解説します。
ご承知おきとは「知っておいてください」
ご承知おきの意味は「これを知っておいてください・認識しておいてください」です。お含みおきよりも、もっとストレートな印象が強くなります。
課員の皆さんには、今週の会議で各自の提案を発表してもらいますので、その点についてご承知おきください
今回の火災訓練は火曜の14時からですので、ご承知おきください
承知は「承知しました」などにも使われる言葉で、簡単な言葉にすると「わかりました」です。この承知に「ご」をつけた丁寧語(敬語ではない)にしたものが「ご承知」です。
![]()
「お含みおき」に比べてストレートな印象が強くなる、というのはこの点です。
「ご承知おき」は目上の人には失礼になる?
結論から言えば、「ご承知おき」を目上の人に使うのは、できれば控えた方が良いでしょう。同じ意味を伝えたいのであれば「お含みおき」を使った方が無難です。
その理由は、やはり「承知」という言葉の印象です。目上の人に「承知しておいて」という意味の言葉を向けるのは失礼になります。
結果は同じでも、命令形で「知っておいてください」と言われるよりも、丁寧に「知っておいていただけるとありがたい」と伝えた方が印象は良くなります。
![]()
「ご承知おき」の例文
今回の案件は、営業部と技術部の合同で行いますので、各自ご承知おきください
前回の会食では、社員の食事マナーの悪さが目立ちました、先方からやんわりと指摘を受けていることは皆さんご承知おきください(次回はみんな気をつけてください、という意味)
毎日の朝礼開始時間が、現在の8時55分から9時に変わりますので、各自ご承知おきのほどお願いします
「お含みおき」「ご承知おき」の違い
「このことを知っておいてください」という意味で使われる「お含みおき」は、「ご承知おき」という言葉と混同されることがあります。
どちらも意味は同じですが、それぞれの言葉が持つニュアンスが違いますので、そこまで知った上で使えると良いでしょう。
まず「ご承知おき」という言葉は「知っておいてください」という表現に似たニュアンスを持っています。
![]()
一方、「お含みおき」という言葉には「これを知っておいていただけるとありがたい」「これは知っておかれた方が良い」という柔らかいニュアンスを持っています。
![]()
違う意味を持った「お含みおき」
「お含みおき」という言葉は通常は「知っておいてください」という意味として使われますが、状況や言い方によっては、思わぬ含みを持たせる言葉に変わってしまいます。
たとえば「例の件ですが、まだ詳しくは言えませんが、何卒お含みおきのほど」などと言われると、「口止め」「密談」「忖度」など、「表だっては言えませんが・・わかっていますよね?」というニュアンスを相手に伝えることになります。
自分自身がそのようなシチュエーションに身を置かなければ、なかなか遭遇しない場面ではありますが、反対に考えると、自分が相手に対しておかしな言い方で「お含みおき」という言葉を使ってしまうと、相手が思わぬ困惑をすることにもなりかねません。
そうならないためには、「何についてどのように知っておいてほしいのか」ということを明確にする必要があります。
「お含みおき」の言い換えに使える類語
「お含みおき」には、「ご承知おき」の他にも言い換えに使える類語があります。
「ご了承ください」
「ご了承ください」という言葉は「お含みおき」の言い換えに使える場合があります。「お含みおき」の意味の中に「理解しておいてください」というニュアンスが含まれているためです。
しかし、「ご了承ください」には、どちらかというと「ご承知おきください」の方にニュアンスが近く、あまり頻繁に使ってしまうと、一方的な印象を持たれてしまう可能性があります。
本日の会議は予定を変更して15時から開始いたします、ご了承ください
交通費の清算は本日中に申請いただいたもののみ、今月の計上としますことをご了承ください
2つの例文は、いずれも「ご了承ください」を「お含みおきください」と、そのまま言い換えることができます。
または、似たニュアンスで伝えたいのであれば「あらかじめお知らせいたします」など、全く別の言い方で伝えるという方法もあります。
たとえば「締め切り後のご応募はお受けいたしかねますので、お含みおきください」を「締め切り後のご応募はお受けいたしかねますことを、あらかじめお知らせいたします」として、「事前にお伝えしておきます」という意味を伝えることもできます。
「ご容赦ください」
「ご了承ください」とも似ているのが「ご容赦ください」です。「ご容赦ください」とは、簡単な言葉に言い換えると「許してください」です。
本日の会議は予定を変更して15時から開始いたします、ご容赦ください
交通費の清算は本日中に申請いただいたもののみ、今月の計上としますことをご容赦ください
この2つの例文は、「お含みおきください」「ご了承ください」に比べて、詫びる要素が強くなっています。それは「ご容赦(許してください)」が使われているためです。
「お含みおきください」が持つ「理解しておいてください」に含まれる「何とかこれで良しとしておいてください」というニュアンスを「ご容赦ください」と言い換えています。
たとえば、「今年の忘年会はインフルエンザの流行により、中止となりますこと、お含みおきください」という文章があったとします。
この文章の意味を、単なる中止を知らせるものとしてだけでなく、楽しみにしていた忘年会が中止となることを詫びる要素を入れたい場合には「今年の忘年会はインフルエンザの流行により、中止となります、ご容赦ください」などともできるということです。