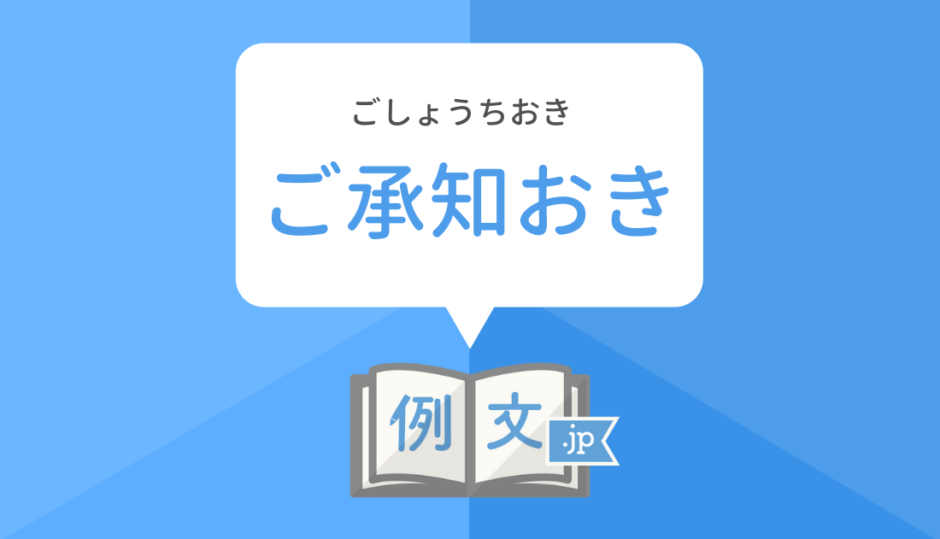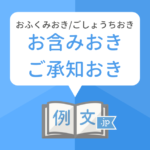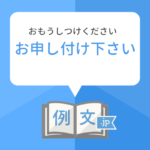目次
ご承知おきくださいの意味
ビジネスシーンなどでよく使われる言葉に「ご承知おき」があります。「承知」という言葉が入っていることから、何となく意味を理解している人は多いかもしれません。
まずは、以下にて「ご承知おき」の意味について解説します。
ご承知おきの意味は「知っておいてください」
「ご承知おき」は、「知っていてください」「理解しておいてください」という意味です。
当日の詳細についてはメールに記載していますので、各自でお読みいただき、内容についてご承知おきください
以上が先日の会議での決定事項です、何卒ご承知おきください
「ご承知おき」は、その意味からやや一方的なニュアンスを出す言葉です。一般的に、人に何かをお願い(この場合は知っておいてください、というお願い)をする場合は、依頼形を使いますが「ご承知おき」に依頼は含まれていません。
![]()
ご承知おきの語源は「承知する」
「ご承知おき」は、動作性漢語名詞の「承知」で「する」の連用形「し」を省略したものです。
そこに「〜している」・「〜しておく」という状態の継続を意味する動詞「置く」の連用形が接続し、さらに丁寧語の「ご」をつけた、丁寧語に属します。
![]()
ご承知おきくださいの例文
「ご承知おき」の使い方と注意点
ビジネスの場で、相手に「これを知っておいてほしい、覚えておいてほしい」と思うことがあります。そんなときに「ご承知おき」を使いたくなるかもしれませんが、この言葉の使い方には注意点があります。
先にもお伝えしたように「ご承知おき」はやや一方的な印象が強い言葉です。そのため、「ご承知おき」を目上の人へ向けると自分の言葉を相手に押し付ける印象となりやすく、人によっては不快感を覚えるかもしれません。

「ご承知おき」の言い換えに使える類語
「今これをどうにかしなければならないわけではないが、情報として後で必要になる可能性が高いので、知って覚えておいてほしい」というときに使えるのが「ご承知おき」です。
以下では、そんなときに使える「ご承知おき」の言い換えに使える類語をご紹介します。
目上の人へは「お含みおき」を使う
目上の人や取引先などに「このことは知っておいて欲しい」と伝えたいのであれば「お含みおきください」を使いましょう。
部長、こちらが来週のスケジュールです、お含みおきいただけますと幸いです
田中様、何かあればご連絡させていただきますが、何もなければこちらからご連絡はいたしませんので、その点についてお含みおきくださいますようお願いいたします
「お含みおき」は「心に留めておいてください」「気持ちの片隅においておいてください」と、感情に対しての要求をする言葉です。

納得してくれれば良い場合は「ご了承ください」
「ご承知おき」のように、今伝えたことを今後も情報のひとつとして覚えておいてほしいのではなく「今この場で伝えるこのことを、ただ了解してくれれば良い」というときには「ご了承ください」を使います。
本日は時間の都合により、報告は書面にてご確認いただきますよう、ご了承ください
感染拡大防止の観点から、会議はリモートにて開催いたしますことをご了承ください
「ご了承ください」は「納得してください・許してください」という意味です。そのため、相手に相談をしているのではなく「こう決めたのでそれでどうか納得してください」とお願いをするニュアンスになります。
「ご承知おきください」と「ご了承ください」の違い
「ご了承ください」
「ご了承ください」というのは「こういうことですから、よろしくお願いします」ということを伝える言葉です。
「こういうことですから」という言い方からもわかるように、基本的には「変更はできないこと」「反対されても覆らないこと」を表します。
「セール品の返品、交換は致しかねますのでご了承ください」というのは「気に入らなかった場合でも返品や交換ができないことはもう決まっていることです、そのことを知っておいてください」という意味です。

「ご承知おきください」
「ご承知おきください」は「今のところこうなっています」「こうなる予定です」という事実だけを表しているため、「一方的な伝達事項」という意味を持ちます。

「ご承知おきください」に返す言葉
目上の人から「ご承知おきください」と文書やメールで告げられた場合は、「承知いたしました」「かしこまりました」などと返します。
「○○の件について承知いたしました」などとすれば、より丁寧ですし「何について承知したのか」ということが明確になります。
また、「了解しました」というのは、目上から目下への言葉ですので、相手が目上の人の場合は使いません。