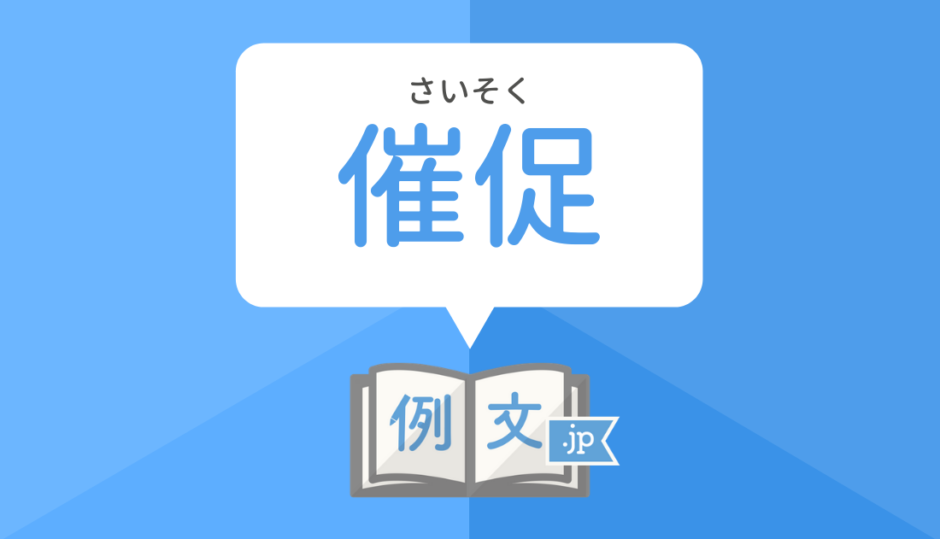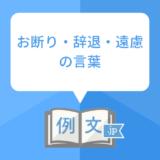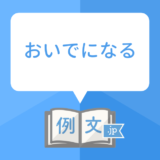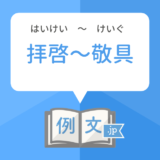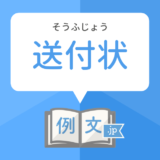目次
「催促」の意味
「催促」には「早くするように推し進めて促す」という意味があります。「催」は「うながす」、「促」は「急がせる」という意味です。
約束を果たすように促すこと
「催促」は主に、相手へ対して「約束を果たすように促す」という意味で使われます。
相手と自分の間にある約束を、相手がなかなか履行しないことについて、早く果たすように推し進めて促すのが「催促」です。
主には、金銭の支払いや業務・納品などの実行が催促の対象となります。
催促のメール例文
先輩社員に資料の提出を催促したい場合
鈴木さん
お疲れ様です。
佐藤です。
先週お願いをさせていただいた「社内アンケート」についてご連絡いたしました。
社内アンケートの提出期日が昨日(3/10)だったのですが、ご提出はいただけましたでしょうか。
私の方で集計をして総務課へ提出をするのですが、鈴木さんのアンケートが見当たらずお伺いさせていただきました。
行き違いであれば申し訳ございません。
もしもまだ提出をされていない場合は、お忙しい中大変恐れ入りますが、本日17時までにご提出いただきたくお願いを申し上げます。
何か不明点などがございましたら、佐藤までご連絡ください。
何卒、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
上司へ返信をやんわりと催促したい場合
鈴木課長
お疲れ様です。
総務部の佐藤です。
本日は、先週お送りした「忘年会への参加についてのお願い」のご返信についてご連絡いたしました。
ご返信の期限が、昨日(3/10)でしたが、鈴木課長からのご返信を見つけることができずお伺いでございます。
行き違いであれば申し訳ございません。
お忙しい中、大変恐縮ではございますがご確認をいただけますと幸いです。
もしもまだご返信いただいていない場合は、本日17時までであればまったく問題ございませんので、ご返信をいただけますでしょうか。
また、何かご不明な点や先週のメールが見当たらないなどございましたら、お手数ではございますが佐藤までご連絡くださいませ。
何卒、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
上司へ社内承認を強めに催促したい場合
鈴木課長
お疲れ様です。
佐藤です。
本日は、昨日口頭でもお話させていただきました「A社様契約の承認」についてご連絡いたしました。
その後、承認の件はどのようになっておりますでしょうか。
A社様には、鈴木課長からの承認が下り次第ご連絡をする、とお約束をいたしております。
しかし、元々の承認予定であった今週の月曜日(3/10)からすでに3日が経過しており、A社ご担当者様も少々困惑されているようです。
私の方からは「社内規定による確認に時間がかかっている」とご説明し、ご納得はいただいておりますが、これ以上お待ちいただくのは難しいと存じます。
鈴木課長がお忙しいことは重々承知いたしておりますが、それを考慮して早めにご依頼をさせていただいた次第です。
本日中にご承認をくださいますようお願い申し上げます。
もしも本日中の承認が難しい場合は、大変恐れ入りますがその旨とA社様にお伝えする理由を、佐藤までご連絡ください。
以上です、よろしくお願いいたします。
「A社からの入金がまだのようです。支払い期日を過ぎているので、催促の手紙を出してください。」
「彼に貸した本がまだ返却されないので、今日にでも返却の催促をします」「支払いが遅れているので、先方から支払いの催促をされました」
「例の件について早く返事が欲しいと、先方に催促をしました」
「催促ばかりされても、こちらは今どうしようもない」
「催促の電話とわかっていたので、居留守を使ってしまいました」
「催促の手段は電話だけでなく、手紙や訪問もあります」
「先日街中でばったりお会いしたときに、見積についての返事を催促しておきました」
「企業として、取引先から納品を催促されているようではだめだ」
「催促される前にやるのがビジネスの基本です」
目上への催促に使える言葉と書き方のコツ
以下では、目上の人への催促に使える言葉と、催促メールの書き方のコツについて解説します。
催促メールに使えるフレーズ
目上の人への催促で「早くしてください」とは、なかなか書けないものです。そこで、以下のようなフレーズを使って催促をします。
- その後いかがでしょうか
- 進捗をお知らせいただけますと幸いです
- 何かお困りのことはございませんでしょうか
- 期日を過ぎましたのでご連絡いたしました
- 〇〇の都合があり、お返事をお待ちしております

催促メールの書き方のコツ
催促メールを書くときにはいくつかのコツがあります。
メールの最初に何の件についての内容かを明記する
例文のように「〇〇の件でご連絡しました」と、メールを開いてすぐに目に入る場所に明記することで、読み飛ばされる可能性が低くなります。
![]()
行き違いである可能性について触れておく
催促をする側としては、行き違いの可能性が極めて低いことは理解しているでしょう。
しかし、目上の人に向けて催促をする場合は、マナーとして「行き違いであれば申し訳ありません」や「〇〇はもうお済でしょうか」などの言葉を使います。

具体的な期日を改めて明記する
催促メールでは「ご返信をいついつまでにください」という内容を含めます。せっかく催促をしても、相手と自分の感覚が異なればまた催促をしないといけなくなるためです。
![]()
「催促」の使い方と注意点
「催促」という言葉は日常会話やビジネスシーンで頻繁に使われています。相手に対して何かを早くするように要求する場面であれば、「催促」を使えます。
しかし、「催促」には明確な言葉のニュアンスが含まれているので、使い方には注意が必要です。
「催促」は敬語・丁寧語ではない
まず、「催促」という言葉自体は敬語でも丁寧語でもありません。「催促」は単なる名詞です。「ご」や「お」をつけて美化することもできません。
そのため「催促」という言葉を向ける相手には注意しましょう。たとえば目上の人に向かって「部長、先日立て替えた出張費を催促します」などとは使いません。
「部長、先日立て替えた出張費を催促します」→「部長、先日立て替えをした出張費の精算をお願いいたします」
このように、目上の人に向けて催促をする場合は「催促」という言葉を他の言葉に変えます。物が対象となっている場合でも「返却を催促します」などとは使いません。
相手が催促の対象でない場合に「催促」を使う
話している相手が、催促をする対象でない場合には「催促」という言葉を使って話せます。
「部長、先日の出張費を経理に催促しているのですがなかなか入金されません」
「この間、お客様にお貸しした傘が返って来ないので催促のお手紙を書いた」
「A社から契約書の確認について催促が来ている、早く対応しなさい」
このように、催促の相手がその場におらず、身内同士で催促する物や事柄について話すときに使います。
「催促」はネガティブな印象の言葉
「催促」という言葉を、催促する対象がいないところで使うのは、催促という言葉自体にネガティブな印象があるためです。
特にビジネスの世界では「相手に急かされて物事を行う」ということを良しとしない慣習があります。また「相手から急かされて何かを行うことを恥じる」という考え方もあります。
これらの理由から、「催促」という言葉にはポジティブな印象がありません。そのために、催促の対象がいる場では「催促」という言葉を使わず、他の言葉に置き換えてやんわりと伝えるのです。
「催促」の言い換えに使える類語
何かを催促したい相手に、催促という言葉を使わずにこちらの意図を伝えるには、類語を使った言い換えが便利です。
ご請求・お支払い
まず、金銭の支払いについて「催促」をしたい場合は「ご請求・お支払い」などの言葉を使うと良いでしょう。
「大変恐縮ではございますが、お支払い期日の○月○日を過ぎております。お手数ではございますが、早急にお支払いいただきますようお願い申し上げます」
「先日お送りいたしましたA製品のご入金確認ができておりません。改めてご請求申し上げますので、○月○日までに当社銀行口座へお振込みいただきますようお願い申し上げます」
ビジネスシーンで金銭の支払いについて催促をする、というのは良くあることです。そのため「催促」という言葉を使わなくても、先方にはこちらの意図を伝えることができます。
ご納品・お納め
次に、製品や商品の納品について「催促」をしたい場合は「ご納品・お納め」などの言葉を使います。
「○月○日に発注させていただきましたA商品についてのご納品をお願いしたく存じます」
「商品代金は○月○日に貴社銀行口座へお振込みしております。早急に製品をお納めいただきたく存じます」
商品や製品を送って欲しい、という催促についても、直接的な「催促」という言葉はほぼ使いません。ご納品・お納めという間接的な言葉を使って、やんわりと催促をします。
ご返却・ご返送
取引先やお客様に、何かを貸し出している場合の返却催促には「ご返却・ご返送」などが使えます。
「貴社○○様へお貸ししている商品サンプルのご返却をお願いしたく、ご連絡いたしました」
「○○様へお貸し出しをいたしました、見本Aのご返送を賜りたく存じます」
商品や物を返して欲しい、という催促にも「催促」という直接的な言葉は使いません。金銭や注文品と同様に、別の言葉でやんわりと返して欲しいという意図を伝えます。
ご来店・ご来社
取引先やお客様に来店・来社を依頼している場合の催促には「ご来店・ご来社」などを使います。
「お電話でもお伝えしましたように、ご契約にはご本人様のご来店が必要でございます。お忙しいとは存じますが、○月○日までにご来店をいただきますようお願い申し上げます」
「メールでもご連絡いたしましたが、今期の商品についての打ち合わせをさせていただきたく存じます。ご足労をおかけいたしますが、一度弊社へご来社いただきますようお願い申し上げます」
相手に来てもらう、というのはお互いの都合が合わなければ実現が難しいものです。金銭や納品の催促よりもさらに丁寧な言い方を心がける必要があります。
「催促」を使った慣用句
矢の催促
「催促」を身内同士で使う場合に、似た意味として挙げられるのが「矢の催促」です。「矢の催促」とは、まるで次々に飛んでくる矢のように、頻繁に行われる催促を表します。
「B社からは毎日、矢の催促だ。よりスピードアップして製品を完成させよう」
「ほんの数日遅れただけで矢の催促とは、先方もよほど余裕がないと見える」
もちろん「矢の催促」も、催促をする相手、もしくは催促をしてきている相手には使いません。あくまでも、相手がいないところで「何度も催促がされている」という状況の説明のためだけに使う言葉です。
居催促
「居催促(いさいそく)」とは、催促をしている相手が、催促をされる側のそばに居座った状態で催促をすることをいいます。催促する人がそばにいる状態が継続されるため、催促される側にとっては大変プレッシャーがかかる状況です。
「担当者が商品を受け取るまで帰らない、と応接室で待っている。居催促とはまいったよ」
「今日こそは居催促をしてでも原稿を受け取って帰ってきます」