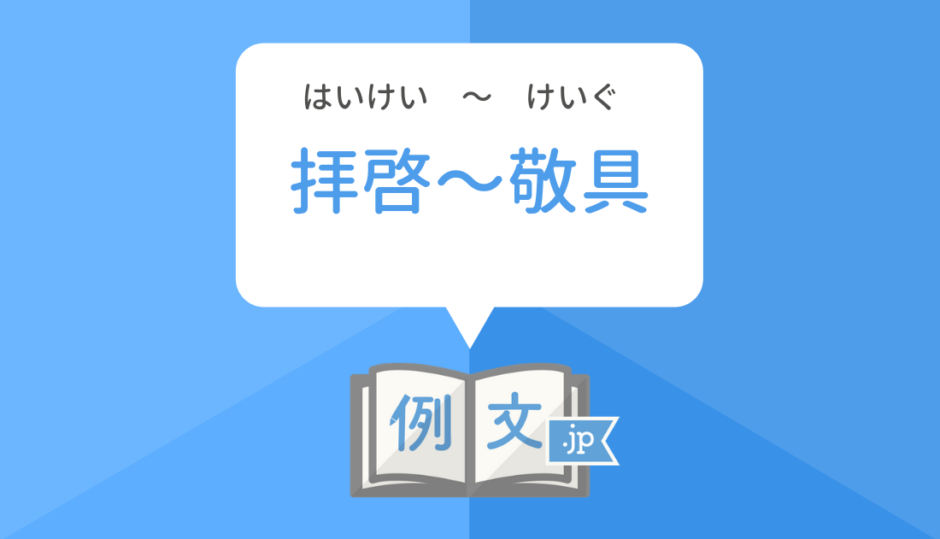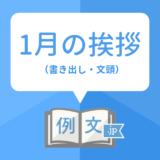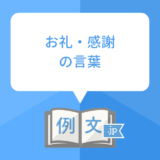目次
「拝啓」「敬具」の意味
相手へのお礼状や、贈答品へ添える手紙などで目にすることが多い「拝啓・敬具」という言葉があります。この「拝啓」「敬具」はセットで使われる手紙ならではの挨拶です。
手紙の最初には「拝啓」手紙の終わりには「敬具」と書かれていますが、この言葉にはどのように意味があるのかご存じでしょうか?
拝啓は「拝んで申し上げる」
「拝啓」を訳すとすれば「拝みながら申し上げます」です。
拝啓の「拝」は拝むという意味です。この場合の拝むは「相手に対してへりくだる、頭を下げる」を意味します。
拝啓の「啓」には出発するという意味があり、この文字を手紙の冒頭に持ってくることで「今から手紙を始めます、申し上げることを始めます」という意味になります。
![]()
敬具は「敬い整える」
「敬具」とは「慎んで申し上げる」という意味の言葉です。手紙の最後に「敬具」と書くことで、「あなたを敬いながら、整えて手紙を終えます」という意味になります。
敬具の「敬」には、相手を敬うという意味があります。「敬語」「尊敬」などにも使われている文字で、敬が使われている言葉はどれも、相手を敬う意味です。
「具」は敬具の場合は「申し上げる」を意味しています。「具」には「そなえる」という意味があり、手紙で相手に言葉を差し出す様子を「そなえる」になぞらえています。
![]()
メールでは拝啓・敬具は使わない
近年では、手紙はよほどのことでなければ書かず、やり取りのほとんどをメールで行っている、という人は多いでしょう。
メールの場合は、拝啓・敬具は不要です。これは、ビジネスメールであっても、友人間でのメールであっても変わりません。先にお伝えしたように、拝啓や敬具は「手紙ならではの挨拶」だからです。
メールでは、拝啓や敬具の代わりに文章での挨拶が使われます。
〇〇様
いつも大変お世話になっております
〇〇様
寒い日が続きますが、お元気でお過ごしのことと存じます
今後ともよろしくお願い申し上げます
お近くへお越しの際はぜひお立ち寄りください
この例文のような文章が、メールでの拝啓や敬具にあたると言って良いでしょう。
![]()
ただし、時候の挨拶についてはメールで使ってはいけない、ということでありません。あくまでも「なくても良い、失礼ではない」と考えておきましょう。
手紙には決まった形式がある
手紙の最初と最後に「拝啓」「敬具」とすれば、その他はどのように書いても良い、というわけではありません。「拝啓」「敬具」が使われる手紙には、その他にも決まり事があります。
(1)「拝啓」の後は「時候の挨拶」
「時候の挨拶」とは、その季節に合った挨拶の決まり文句です。時候の挨拶は月ごとにいくつかありますので、自分が使いやすいものを選びましょう。
たとえば1月なのであれば「新春の候」、2月であれば「向春の候」などです。
(2)「時候の挨拶」の次は「気遣いの言葉」
「時候の挨拶」の次には相手を気遣う言葉が入ります。「ますますご健勝のことと存じます」などが代表的でしょう。
時候の挨拶と並べると「新緑の候、ますますご健勝のことと存じます」となり「○○な季節になりましたね、きっと元気にされていますよね」という意味です。相手へ語りかける冒頭の挨拶になります。
(3)「気遣いの言葉」の後には「御礼・感謝」
「気遣いの言葉」の後には「いつもありがとうございます」という意味の「御礼・感謝」の言葉が入ります。
「○○様には、いつもお心にかけていただき心より感謝申し上げます」など「いつもありがとう」「いつもお世話になっています」という内容を伝えるのです。
拝啓 新緑の候、ますますご健勝のことと存じます。○○様にはいつもお心にかけていただき、心より感謝申し上げます
ここまでが手紙の冒頭の挨拶文です。この次からやっと用件に入ることができます。
(4)用件のまとめ
用件を書き終えたら、手紙の内容のまとめ文を入れます。
「まずは略儀ながらお礼かたがたご挨拶申し上げます」など、手紙の内容にあった言葉を書きましょう。「今日はこういう用件でした」と改めて用件を振り返ることで話しを締めます。
(5)「用件のまとめ」の後には「季節に絡めた気遣いの言葉」
時候の挨拶とは別に、文末では「季節に絡めた気遣いの言葉」が入ります。
寒い季節であれば「日に日に寒さが厳しく感じられます、どうかご自愛くださいませ」などでしょう。「○○な季節だから、身体を大事にしてくださいね」ということを伝える文章です。
(6)「季節に絡めた言葉」の後には「敬具」
ここで「敬具」が入ります。「以上の内容を、あなたを敬いながら終えます」という挨拶です。
「敬具」の後には、日付と名前を入れて、手紙は終わりです。
(7)「かしこ」は女性専用の言葉
「敬具」の代わりに使える言葉のひとつに「かしこ」があります。この「かしこ」には、「かしこまりました」という意味があり、手紙の最後に内容をまとめて終える、という役割があります。
しかし、この「かしこ」は女性しか使えません。手紙を宛てる相手が男性であっても使用できますが、手紙を書いている人物が女性の場合しか、「かしこ」は使えませんので注意しましょう。
![]()
「拝啓・敬具」意外の手紙の挨拶
「拝啓・敬具」のセットは一般的に多く使われています。相手への敬意を表しながらも、丁寧過ぎず使いやすいためです。しかし状況や相手によっては、もっと別の挨拶の方が効率的であったり、相応しいということもあるでしょう。
「前略」「早々」
この「前略」という言葉とおり、「前置きを省略します」という意味を持つ挨拶は使う状況や相手が限られます。
まず、「とても急いで伝えないといけないことがある」「まずはこれだけ伝えたい」など、非常に急いでいる状況であり、かつ、相手がある程度気心の知れた人であることです。
文末の「早々」にも「早々と終わります」という意味がありますので、敬意を表さなければならない相手へは相応しくありません。
「謹啓」「敬白」
この表現は「拝啓・敬具」よりも丁寧で格式高い挨拶です。
相手が上司やお客様、取引先の方など、最大限の敬意を表さなければならない手紙に使われています。
とても配慮の感じられる挨拶であるため、相手の方との関係が深くない場合でも、安心して使うことができるでしょう。
「拝啓・敬具」を使わない手紙
手紙の内容や、受け取る相手によっては「拝啓・敬具」が逆効果となることもあります。
とても親しい人への手紙
上司や同僚など立場によらず、自分と相手の関係が良好な場合は「前略・早々」などに留めた方が良いでしょう。
手紙とは言っても、実際の関係とかけ離れた丁寧な挨拶は相手との距離を広げてしまいます。
何らかの失礼があった相手へ出す「詫び状」
「詫び状にこそ使った方が良いのでは?」と考えてしまいがちですが、詫び状は基本的には拝啓や敬具を使いません。
詫び状というのは「一刻も早く謝罪の気持ちを伝えるため」の手紙です。「拝啓・敬具」を使って時候の挨拶などの流れを追って書いてしまうと「のんびり書いているな」「緊迫感が伝わらない」と相手に間違った心象を伝えてしまいます。
詫び状であれば、いきなりお詫びから始めても良いですし、拝啓に代わる言葉を使う場合は「急啓(きゅうけい)・敬具」です。
急な病気のお見舞い状
急な病気のお見舞い状の場合も「急啓(きゅうけい)」を使います。この「急啓」とは「急ぎ申し上げます」という意味です。
急啓はお詫び状やお見舞い状など、急いで伝えたい(伝えなければならない)内容の頭語に使われます。
前文が無い手紙への返信
頭語や結語・前文などを用いない手紙に対しての返信にも、拝啓・敬具などは使いません。